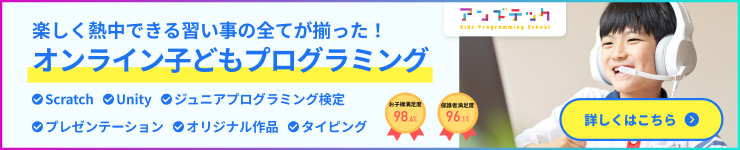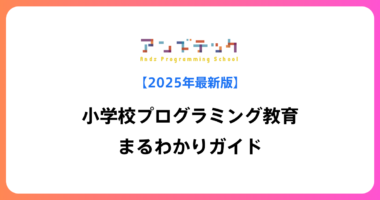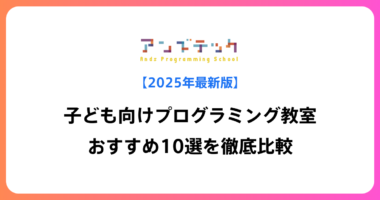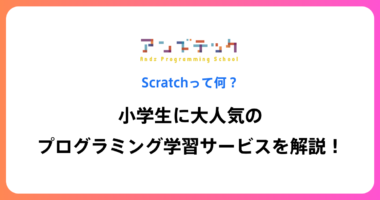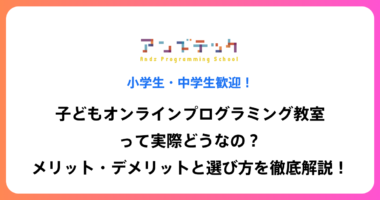「プログラミングの習い事には意味がない」は本当?教室運営者が考えるプログラミングの意味
子どものプログラミングの習い事は意味ない?費用や向き不向き、小学校との違いを教育のプロがやさしく解説します。
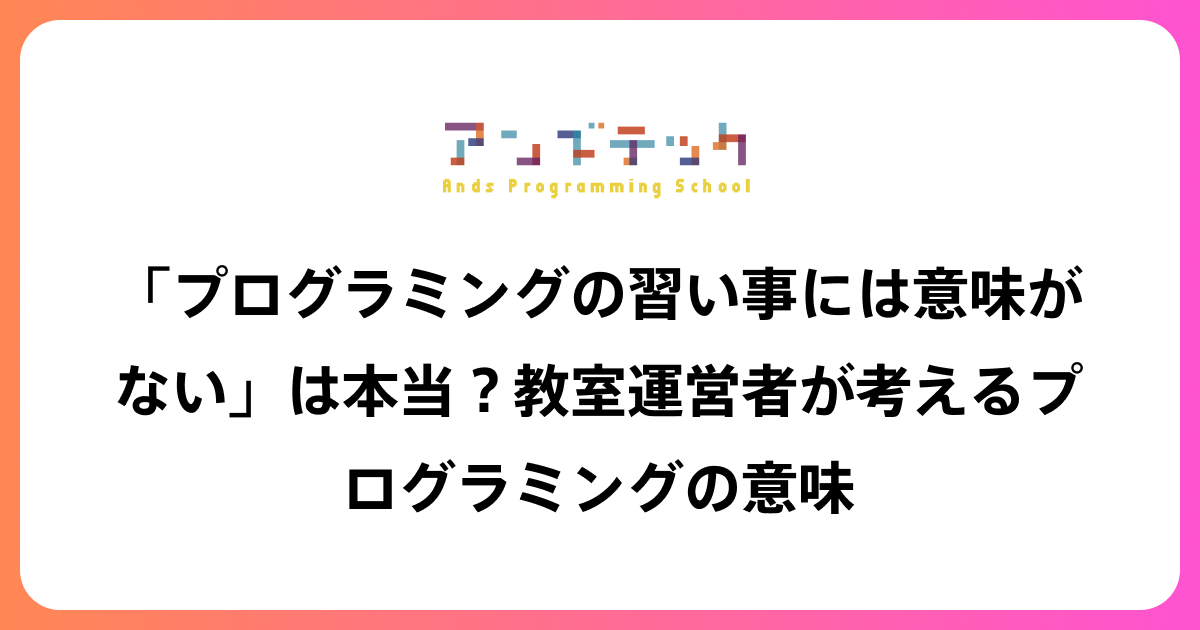
「子どものプログラミングの習い事って、意味あるの?」
と思ったことはないでしょうか。
というのも、ここ数年で「プログラミング教室って最近よく聞くけど、うちの子にも必要?」と悩んでいる保護者の方がすごく増えたなあ、という実感があるからです。
検索ワードでも「プログラミング 習い事 意味ない」「小学生 プログラミング 習わせるべきか」というものがよく見られます。つまり、多くの人が「やったほうがいいのかどうか」で迷っている、ということなんですよね。
でも、正直にいうとそのモヤモヤ、すごくよく分かります。
昔からある習い事って、水泳とかピアノとか、なんとなく「やっておくと良さそう」という空気がありますよね。
でもプログラミングって……なんかまだよく分からないし、パソコンとかゲームのイメージが強くて「本当に教育として意味あるのかな?」と不安になる気持ち、あります。
それに加えて、ネットで「プログラミングは意味ない」「遊びで終わる」といった声を見かけたりすると、ますます迷ってしまうものです。
とはいえ、プログラミングは子どもたちにとって、これからの時代を生きるうえで避けて通れないスキルでもあります。
しかもそれは、必ずしも「エンジニアになる」ためだけのものではない、というのがポイントです。
この記事では、「プログラミングの習い事って実際どうなの?」という疑問に対して、プログラミング教室運営者であり、教育にもテクノロジーにも日々向き合っている立場から、できるだけわかりやすくお話してみようと思います。
結論を押し付けるのではなく、「あ、ちょっと考え方が軽くなったかも」と感じてもらえたら嬉しいです。
というわけで、いってみましょう。
▼楽しく学べるプログラミング体験なら「アンズテック」
お子様にプログラミングを楽しく学ばせたいとお考えの保護者様に、アンズテックのオンラインレッスンがおすすめです。まずは、無料体験レッスンにお申込みください。
▼ アンズテックについて詳しく知りたい方はこちら
>> 「アンズテック」の公式サイトを確認する
目次
「これからはプログラミングの時代です!」って言われるけど…

最近、「プログラミング教室って将来のために通わせるといいですよ!」みたいな話、よく見かけませんか?
たとえば、
- IT人材が不足する時代に備えましょう
- これからはプログラミングが読み書きそろばん並みに大事です
- 子どもが小さいうちから論理的思考を鍛えておくべき!
……というようなものです。
うん、正論なんですよ。わかります。
言ってることは確かにそうだと思う部分もあります。
でも、それって言われる側の立場からすると、圧を感じるというか、プレッシャーになっていないですか?
「うちの子、今のところゲームしか興味ないけど……それってまずいの?」とか、
「私たち親がそこまでIT詳しくないのに、ちゃんと見守れるのかな?」とか。
要するに、「プログラミングが必要って言われるけど、なんとなく信じきれない」ってことなんですよね。
あと、「論理的思考力が育つ」とかって、すごく良いことのように聞こえるんですけど、
じゃあそれって日常生活のどこで役立つの?って思ったりもします。
いやいや、急に難しい言葉言われても、ちょっと待って?みたいな気持ちになりますよね。
プログラミングの習い事をする人は、将来プログラマーを目指している?
とはいえ、子どもの習い事って、「意味があるから通わせる」だけじゃないですよね。
たとえば、水泳だって、オリンピック選手を目指してる子ばかりじゃないし、
ピアノだって、音大に行くために始めたわけじゃない家庭も多いはずです。
それと同じで、「プログラミングを将来の仕事にするかどうか」は置いておいて、
「学ぶことでどんな成長があるのか?」を見てみると、またちょっと違う景色が見えてきます。
というわけで、次の章では「なんか不安なんだよね…」という保護者のリアルな気持ちに、もう少し深く寄り添ってみようと思います。
「費用が高そう」「遊びっぽくて不安」「ちゃんと身についてるの?」
そんな“あるあるな不安”を整理しつつ、一緒に見ていきましょう。
プログラミングの習い事に対して「不安」ありますよね

プログラミングの習い事って、なんかよさそう。
でも、なんとなく不安もある。
そんな声、ほんとうによく聞きます。
私達のスクール(アンズテック)に体験に来る保護者の方、ほとんどがそんな不安をお持ちです。
うちの子に向いているかわからなくて…
いちばんよく聞くのは、「ウチの子に向いてるか分からなくて……」という相談です。
たとえば、
- ゲームは好きなんだけど、ちょっと飽きっぽい
- 機械が得意な感じでもないんですよね
- プログラミングって“理系の子”がやるイメージがある
こういう不安って、すごくよく分かります。
ただ、これを聞かれたとき、正直「向き不向きって、あんまり関係ない」と思っています。
その理由は、それより「好きでいられるかどうか」が一番大事だからです。
よく「この子に向いてるかどうか」で悩む方がいるんですけど、
正直やってみないと分からないんですよね。
というのも、プログラミングだけに限らず、習い事というのは結局「やり続けられるかどうか」がいちばん重要です。
そして、「やり続けられるか」は、その子の性格とか才能だけではなく…
- 嫌がらずに続けられるか
- 先生や仲間に恵まれたか
- 「自分でもできるかも」って思える瞬間があったかどうか
……など、お子様の性格だけではなく偶然の要素や、時間が経って初めてわかることも含まれてくるからです。
だから、「向いてそうに見えるから続く」とか、「飽きっぽいから無理そう」というのは、実はあんまり関係ないのではないでしょうか。
むしろ大人が「これはおもしろいかも?」とちょっと投げかけてみるだけでも、全然違ったりします。
ピアノや水泳だって、そんな感じで始めた人、きっと多いはずです。
私自身も学生時代に軽い気持ちでプログラミングを始めてみて、当時はこんなに長くハマり続けるとは全く思っていませんでした。
なので、軽い気持ちで始めてみて、自分に合うなら続けてみる、という心持ちで良いと思います。
月謝、高くないですか?
これ、本当にわかります。
プログラミング教室の月謝はおそらく中央値で1万円程度。教室によっては月数万円になることもあります。
ほかの習い事にも通っていたら、けっこうな負担です。
特に、兄弟姉妹で習い事をしている家庭だと、「どれを優先するべきか」で迷うこともありますよね。
「これで途中でやめたらどうしよう…」「値段に見合う内容なの?」という不安が出てくるのも、無理ないと思います。
高い理由は色々ありますが、プログラマーの時給がそもそも高い!というのは理由の一つとしてあります。
プロのプログラマーは時給換算1万円程度の人がゴロゴロいる世界なので、まともなプログラマーが講師をやると値段が高くなりがちというのがあります。
プログラミングの成長ってどんなことがあるの?
また、不安を感じる要素として、プログラミングの習い事は成果が“見えづらい”と言われます。
たとえばピアノだったら、曲が弾けるようになったらすぐ分かるし、水泳もタイムや級がはっきりしています。
でもプログラミングは、画面をカチャカチャやってるだけに見える。
「これ、本当に意味あるの?」という気持ちになるのも、自然です。
でも実は、そういう不安を感じているのって、みなさん一緒です。
なので、「わたしだけが迷ってるのかな…」と思わなくて大丈夫です。
ここから先は、じゃあ「実際のところ、プログラミングを習うってどんな意味があるの?」というところを、もう少し具体的に見ていきたいと思います。
プログラミングは、全員が習わなくてもいい。でも、「体験しておくといいことが多い」のは事実。

「結局のところ、プログラミングって、やらせたほうがいいんですか?」
という疑問を持っている方は多いですよね。
個人的な考えとしては「べつに全員が習う必要はないと思う」というのが正直なところです。
…おいおい、自分で教室やってるのに何言ってるんだって思いますよね(笑)。
でも本当にそうで、「全員に必要!」と言いたいわけじゃないんです。
ただし。
体験として、やってみるのはすごくいいと思ってます。
考えるトレーニングとしては抜群に効果的
なぜかというと、プログラミングって、「将来のためのスキル」っていうよりも、「考えることのトレーニング」に近いんですよね。
たとえば、子どもがScratchでゲームをつくろうとするとします。
で、こう考えるわけです。
「キャラがジャンプするには、どういう命令を出せばいいんだろう?」
「スタートからゴールまで、どういう流れにすればいいかな?」
「うまく動かないとき、どこが間違ってるのか見つけないと…!」
これって、いきなり正解があるわけじゃなくて、考えて、試して、間違えて、やり直して……の連続なんですよ。
この試行回数が圧倒的に多い。なぜなら、間違えてもすぐにその場でやり直せるから。
料理とかでは、一度間違えたらやり直すのが難しいのですが、プログラミングの場合は、即座に元の状態に戻すことができます。
何度も試して、思い通りのものに近づけていくのがプログラミングでやっていることです。
成功体験が多いから自信につながる
しかも、うまくいったらちゃんとゲームが動くんです。
「あ、できた!」
この瞬間、めちゃくちゃテンション上がります。
ほんとに、見てるこっちまでうれしくなります。
これは「自分が頭で考えたことを、ちゃんと形にできた」っていう他にはない特別な体験なんですよね。
大人でもなかなか味わえない快感なので、一度体験するとプログラミング沼にハマってしまいます。
プログラミングができたからといって、それで未来の安定が確定するわけではありません。
でも、「自分で考えて、手を動かして、形にできた」という経験は、どんな分野に進んでも、とっても力になると思ってます。
失敗が当たり前のプログラミングだから、チャレンジする体験が可能になる。
それに、「思い通りにいかないことに向き合う」練習にもなるんですよね。
途中でバグが出たり、うまく動かなかったりするのが当たり前ですので
プログラミングの授業って、うまくいかない時間が、めちゃくちゃ大事なんです。
なので、やってみて「楽しい」と思える子には、
ちょっと続けてみるだけでも、すごく意味のある習い事になります。
別に「将来エンジニアに!」とかじゃなくて全然OK。
むしろ、「なんかちょっと楽しいかも」が入り口でいいんです。
じゃあ、プログラミングは意味があるってこと?

ここまで読んで、「あれ?プログラミングって、思ってたより良さそうじゃない?」と思ってくださった方もいるかもしれません。
でも、そこで出てくるのがこの疑問。
「で、実際、なにが身につくんですか?」というやつです。
はい、正直に言って、この質問には私もちょっと悩みます(笑)。
なぜかというと、プログラミングって、
“見えにくい成長”が多いんです。
ピアノなら、「この曲が弾けるようになった」とか
水泳なら、「25m泳げた!」とか、目に見えるゴールがあるんですけど、
プログラミングは、そういう「わかりやすい成果」がちょっと見えづらいんですよね。
でも、ちゃんとあります。
子どもたちは、知らないうちにすごくいろんな力を育ててるんです。
たとえば、こんなことが起こります。
タイピングが速くなる
まず地味だけど確実に、「キーボード慣れ」します。
タイピングができるようになると、将来の宿題やレポート作成もスムーズです。
タイピングの結果は数字で現れるので成長がわかりやすいです。
パソコンに対する苦手意識がなくなる
「子どもにパソコンを使わせるのが怖い」っていう声も多いんですけど、
使い方を知っておけば、変な怖さが減ります。
スマホだけじゃなく、“何かを生み出すための道具としてパソコンを扱う”経験は、けっこう大事です。
発表やプレゼンに強くなる
アンズテックでは、自分が作ったプログラミングの作品を発表する時間があります。
「何を作ったか」「どうやって工夫したか」を、人に伝える練習です。
最初はみんな恥ずかしがるんですけど、
慣れてくると「もっと発表したい!」って言い出す子もいるんですよ。
プレゼン力、自然と育ちます。
考える力・試す力・諦めない力
何度も出てきてますが、ここが一番大きいです。
「どうすれば思い通りに動くか」を考えて、
「やってみて」「うまくいかなくて」「もう一回やってみる」っていうプロセス。
これを繰り返す中で、子どもたちって自然と
“手を動かして考える”ことに慣れていくんですよね。
もちろん、すべての子に同じ変化が起こるわけではないです。
でも、アンズテックを利用してくれている子どもたちを見ていると、
「学校の勉強とはちがう種類の成長」をしているのをよく感じます。
それってたぶん、“うまくいかないことに向き合う”経験ができるからなんだと思います。
というわけで、「将来に直結するスキル」みたいな、分かりやすいラベルは貼りづらいかもしれませんが、
プログラミングの習い事には、ちゃんと“育ってる力”があります。
でも、ここまで聞いて「やっぱりちょっと遊びっぽく見えるんだよな…」と感じた方もいるかもしれません。
その感覚、実はけっこう大事なので、次のパートでは「遊びで終わるのでは?」という疑問について考えてみたいと思います。
プログラミングの習い事によくある誤解をちょっとだけ整理します

さて、ここまでプログラミング教室の話をしてきたんですが、
「いやいや、それでもさすがに遊びで終わるんじゃないの?」という声もあります。
はい、めちゃくちゃ分かります。
私もプログラミング教室を始めたばかりの頃、
「ゲームをつくる授業?え、それってただ遊んでるだけじゃないの?」と言われました。
ここで大事なのは、“遊びかどうか”よりも“どんな遊びなのか”なんですよ。
遊びながら学べるのがプログラミング
たとえば、
砂場でダムを作って水を流すのも「遊び」ですよね。
でも、それって実は水の流れや重力を学んでるわけで、立派な理科の入り口です。
プログラミングもそれと似ていて、
「遊びながら考える」ことができれば、それはもう立派な学習になります。
ただし、ひとつ注意があります。
それは、学校や教室によってぜんぜん中身が違うということです。
同じ「プログラミング教室」でも、
- ただゲームをプレイして終わってしまうところ
- つくる過程にしっかり頭を使わせてくれるところ
この差はとても大きいです。
なので、「遊びで終わるかどうか」は、通う場所によるというのが正直なところです。
そしてもう一つ、よくあるのがこの誤解です。
プログラミングは独学で十分では?
「プログラミングなんて、無料アプリとかYouTubeとかで学べるでしょ?」
これも正しいようで、実はちょっとだけ違います。
たしかに、最近はすごく良い教材がネット上にたくさんあります。
Scratchも無料だし、動画も豊富だし、家でも学べる環境は整っています。
でも……それを「続けられるかどうか」が最大の壁なんです。
想像してみてください。
家で小学生が、一人で静かに、毎週コツコツと、タイピングの練習をして、
ゲームを作って、つまずいたら自分で調べて、最後まで完成させる。
……たぶん、9割くらいの子は途中でやめちゃいます。
そもそも、自分で「どこまでやるか」や「何をつくるか」を決めるって、けっこう難しいんです。
大人でも「ひとりで黙々と勉強し続ける」って難しいのに、子どもだったらなおさらですよね。
だから、教室に通う意味って、
「続けやすい環境があること」
「つまずいた時に助けてくれる人がいること」
「“できた!”を一緒に喜んでくれる誰かがいること」
このあたりがすごく大きいと思っています。
もちろん、独学でできる子もいます。
でも、それはごく一部の例外。
多くのお子様にとっては、「習い事として定期的に学べる環境」のほうが向いていると感じています。
というわけで、
「遊びで終わるかもしれない」「家でやればいいんじゃないか」という考えにも、
ちゃんと理由があるとは思うんですが、
そこにちょっとだけ視点を足すと、また違った判断ができるかもしれません。
次は、「じゃあ、学校の授業とプログラミング教室って何が違うの?」という話をしていきます。
ここもけっこう誤解が多いところなので、サクッと整理してみますね!
小学校のプログラミングの授業で十分では?

ここまで来ると、よくこういう声も聞こえてきます。
「え、小学校でもプログラミングって今は習うんですよね? それで十分じゃないの?」
はい、その通りです。
プログラミング、いまは小学校で“必修化”されています。
でも……これ、名前は同じでも中身がぜんぜん違うんです。
小学校でプログラミング教育がはじまった理由は、ざっくり言えば「物事を順序立てて考える」という部分にフォーカスされています。
これがいわゆる「論理的思考力」とか「プログラミング的思考」と呼ばれるものです。
それ以外の理由としては
- コンピュータや情報技術がどのように使われているかを理解する
- プログラミングを通じて、算数や理科などの教科の学びを深める
- プログラミングと社会の関わりを考える
などが挙げられています。
プログラミングスキルの習得が目的ではない。ということです。
実際に学校では、パソコンやタブレットを使わずに考え方だけを学ぶ学校もありますので、
考え方の部分にフォーカスされていることがわかります。
一方で、プログラミング教室ではどうかというと、
実際にパソコンやタブレットを使って、自分でゲームやアプリをつくってみるというところまでやります。
もちろん、「考える力」も必要なんですけど、
それを手を動かして形にしていくプロセスがあるんですね。
たとえば、
- 自分でキャラクターを動かしてみる
- スコアをカウントさせる
- ゲームオーバー画面をつくる
といったことを、子どもたちが自分でやっていきます。
ここが大きな違いで、
学校は“きっかけを作る場所”、教室は“深める場所”のような関係性だと、私は思っています。
なので、「学校でもやってるし、それで十分でしょ?」ということに関しては、少し違いがあります。
他の教科で例えると、家庭科の授業で料理をすることはあるけど、
じゃあ一人で料理ができるようになるかというとそうではない、という感覚に近いです。
もちろん、小学校の授業にもすごく意味があります。
でも、やっぱり“実際に作ってみる”という体験は、別の価値があるんですよね。
というわけで、
「学校の授業でやってるからいいかな」と思っていた方も、
「もうちょっと深く触れてみるのもアリかも?」と感じてもらえたらうれしいです。
最後に「アンズテック」の教室について紹介させてください!
ここまでいろいろ書いてきましたが、せっかくなのでちょっとだけ私たちの教室「アンズテック」の紹介もさせてください。
アンズテックは、子ども向けのオンラインプログラミング教室です。
小学生〜中学生を中心に、Scratch(スクラッチ)やUnity(ユニティ)などのツールを使って、自分だけの作品をつくるということを軸にしています。
「作品ってなに?」というと、
たとえば、
- 自分で考えたルールのゲーム
- おみくじアプリ
- キャラクターがしゃべるアニメーション
- 自分で操作するRPGみたいなもの
などなど、“頭の中にあるものを、プログラミングを通じてカタチにする”のがゴールです。
「できた!」という体験が成長につながる

アンズテックで大事にしているのは、
「できた!」の積み重ねです。
よくある話ですが、プログラミングは、ちょっと難易度が上がると、いきなり「分からない」ゾーンに突入することがあります。
そうなると「もういいや〜」ってなりがちなんですよね。
でも、私たちはあえて“ちょっと頑張ったらできそう”なサイズのチャレンジを用意しています。
チャレンジして間違えることがあっても、講師がついているので安心して失敗できる環境になっています。
発表に強いプログラミング教室

さらに、作品を発表する機会もちゃんとあります。
「人前で話すの、苦手なんです…」という子も多いですが、
無理にやらせるのではなく、「伝えたい」って気持ちが出てきたときに、ちゃんと場を用意するというスタイルです。
毎回授業では発表の時間を設けて、全員が発表をします。
さらに定期的に発表会だけのイベントも開催して、どんどん自分の考えを共有する機会をつくっています。
少人数制でひとりひとりと向き合いながら学べる

少人数制なので、ひとりひとりとしっかり関われるのも、アンズテックのいいところです。
保護者の方からは、
「子どもが自分から進んでやるようになった」
「家でタイピング練習してるのにビックリしました」
「母の日に私のためのアプリを作ってくれました」
といった声をいただき、理想的な環境になっていると感じています。
まとめ「プログラミングの習い事に意味はある」

ここまで、「子どもにプログラミングの習い事って意味はあるの…?」というテーマでいろいろ書いてきました。
最後に私なりの結論をひとことで言うと……
プログラミングの習い事には、ちゃんと意味があります。もちろん、必ずしも全員が習うべき!とは思っていません。
でも、「体験として触れておくこと」には、大きな価値があると実感しています。
それは、たとえば、
- 自分で考えて、試して、つくって、失敗して、やり直すこと
- わからなかったことが「できた!」になる瞬間のよろこび
- 誰かに見せたくなる、自分の作品があること
こういう経験って、たとえ将来プログラマーにならなくても、
「生きる力のひとつ」になるんじゃないかと思うんです。
「プログラミングはツールだ」なんてよく言われますが、
そのツールを通じて、自分の頭で考えたり、誰かと話したり、表現したりすること。
そういう時間を、子ども時代に持てることは、とても貴重な経験だと思ってます。
少なくとも私は子ども時代にそんな場所がほしいと思っていました。
というわけで、
もしちょっとでも気になっていたら、まずは一度体験してみてください。
正直なところ、やってみないとわからないです。
でも、やってみたら「思ってたよりおもしろいかも?」となる可能性は高いです。
アンズテックもそのひとつの場所として、お待ちしています。
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました!

アンズテック子どもプログラミング教室
アンズテックは、小中学生向けの完全オンラインプログラミングスクールです。ScratchやUnityを使い、子どもの興味に合わせた楽しいカリキュラムで、創造力・思考力・ITスキルを育みます。全国どこからでも現役プログラマーの受講が可能!